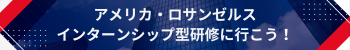インターンシップ体験談:課題解決型コース
立命館アジア太平洋大学国際経営学部 2年生(参加当時)村上真斗さん

参加理由
参加した目的は大きく分けて2つあります。1つはこれから必要になるであろうスキルを磨くため。2つ目は英語力をつけることです。
一つ目の必要になるであろうスキルというのは、具体的にいうと「問題発見能力」と「問題解決能力」、そして「実行力」です。なぜこれらが必要になると思うかというと、今後AIなどのテクノロジーがますます私たちの生活に入ってきて、今ある職業の半分はなくなったり、それらテクノロジーにとって代わったりするとされているからです。そんな中で、私たちが生き残るためには人間にしかできないことやテクノロジーよりも優れている部分を伸ばしていくことが重要だと思います。それは「考える力」であり、「0から1を生み出す力」だと私は考えています。つまりそれは、問題を見つけ、それを解決していく能力であり、それらをチームで行動し、実行していける力だと思います。
それらのスキルをこのグローバル・キャリア・プログラムを通じて学べると感じたから参加しました。このプログラムの中でも「課題解決型のインターン」はそれらを養うことができると感じました。与えられた課題に対してすべて自分たちで考えて成果物を出すという一連の流れを通して、何が問題かを捉え、その問題に対してどのようなプロセスを踏んでいくかをチームで考えていくことができ、先に述べた能力、スキルを獲得できると感じたからです。
もう一つの理由は、英語力をつけたいと思ったからです。英語が話せるというのは、これからの時代、国内で働くにしても必要になっていく重要なスキルだと考えています。大学でも使う機会はありますが、より生きた英語を、それも一か月という期間、聞ける、そして話さないといけないという環境に身を置くことは、私のこれからのキャリアにとってとてもインパクトのある経験になると思い、参加を決めました。
参加する前に思っていたこと
楽しみだったことは、アメリカを感じることができるという点です。まともに海外に行ったことがなかったので、純粋にアメリカ、LAに行けることは楽しみでした。特に本場のNBAを見に行くことは楽しみにしていました。また、現地の人と交流できることも楽しみでした。私の目標として、観光地に行くというよりも現地の人と交流して、アメリカの生活スタイルといった文化に触れたいと思っていたので、たくさん話して交流することが楽しみでした。
プログラムの内容で楽しみだったことは、課題解決型のインターンの中で、チームで議論を重ねながら「あーでもないこうでもない」と言って良いものを作っていくプロセスだったり、現地の人にインタビューしたりすることでした。
逆に不安だったことは費用の面です。やはり、日本より物価が高く、何かとお金がかかるだろうなと思っていたので、どのくらい生活費だけでお金がかかるのかは不安でした。しかし、せっかくの機会なのでやりたいことには惜しまず使おうと思っていました。また、お金をかけずともアメリカを感じられることや、学べること、楽しめることはたくさんあると思っていたので、そこを意識して一か月間過ごそうというのはプログラム前から意識していました。
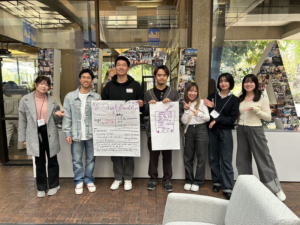
インターンシップについて
【行ったタスクとスケジュール】
- インターン初日:会社説明、自己紹介、ネット契約リサーチ、目標設定
- インタビュー設計と実施(例:ターゲット探し、プレゼンテーション相手の抱えている過大など)
- アンケート調査(合計100件以上)
- ターゲット設定、プラン設計、プレゼン資料&スクリプト作成(英語と日本語)
- 最終プレゼンテーションの実施
【午前】 ・出社(時間通りにオフィスに集合) ・チームミーティング(1日のゴールと役割分担の確認) ・リサーチ、インタビュー準備や調査活動
【昼】 ・スタッフやメンバーとランチ(ここでコミュニケーションも深まりました)
【午後】 ・プレゼン資料作成やインタビュー実施 ・フィードバックの反映と修正作業 ・通常業務(同時並行) ・進捗報告と翌日の準備

実習で印象深かったこと、大変だったこと
印象深かったのは、社員の皆さんの“メリハリ”の凄さです。指摘すべきことはしっかり伝えながらも、その後は和やかな雰囲気に切り替えたり、ケーキを食べながら笑い合ったりするなど、切り替えが非常に上手でした。これは私にはまだできないことで、言われたことを引きずってしまったり、感情の切り替えが遅かったりする自分との差を実感しました。
また、就業時間になったらすぐ各々がやるべき業務に集中し、休憩時間には楽しくおしゃべりするなど、効率よく過ごしていて、働き方としてとても印象に残っています。おそらく、業務がマルチタスクで同時進行のものが多いため、効率を追求せざるを得ない状況にあるのだと思います。
逆に大変だったのは、短期間で成果物を出すプレッシャーです。2週間という期間で、ターゲット決めからプラン構成、アンケート調査、資料・スクリプト作成まで全て行う必要があり、常に時間に追われながらの実習でした。
特に2つの言語(英語と日本語)での作成は大変でしたし、データの根拠づけやロジカルな構成にも苦戦しました。もっと早くからチーム内で目的の共有や方向性の確認をしていれば、より良いプレゼンや成果物を残せたかもしれないと思いました。

実習中に最も努力したこと
実地研修中に私が最も努力したことは、インクルーシブなチームにするために、相手が意見を言いやすい雰囲気をつくることです。具体的には、相手の意見を否定せずに傾聴することや、メンバー一人一人の意見を聞くために「どう思う?」と意見を求めたり、確認することを意識して行っていました。
ただ、ずっとそれができていたかというと正直そうではありません。できていなかった時もありましたし、もっと積極的に行動に移すべきだったと反省もあります。また、相手の意見を聴くことや否定しないことを意識しすぎるあまり、自分の意見を言えなかったり、疑問が残ったまま進んでしまったりした場面もありました。
そのため、結果として本当にインクルーシブなチームにはできなかったと思います。ですが、この努力を通じて「チームにおける多様な声の大切さ」や「自己主張と傾聴のバランスの難しさ」に気づくことができたことは、今後の学びにつながると感じています。

ホテルでの共同生活について
よかったこと・悪かったこと
ホテルステイの環境はとても満足のいくもので、本当に良かったです。ホテルのコンセプトである「家にいるようなサービスや設備」の通りで、キッチンや大きな冷蔵庫、ふかふかのベッドなど、快適な生活を送ることができました。スタッフの接客も素晴らしく、元気に挨拶してくれたり、アメリカ生活でわからないことを親身に聞いてくれたりと、温かいサポートに助けられました。
悪かったことは特にはありませんが、あえて挙げるとすれば「生活の慣れによるマンネリ化」があったことです。ホテルは3週間ずっと同じ場所での生活になるため、後半になると新鮮味がなくなり、生活に慣れてしまっていたように思います。ホームステイであれば、途中で環境が変わることで新しい刺激や気づきが得られると思いますが、ホテルステイはずっと同じ場所だからこそ「深く知る」ことができる良さがあります。
実際に私は、滞在したトーランスの街をよく歩き、いろいろな角度から街を知ることで、町のコアな部分まで知ることができました。それは、課題のヒントにもなりましたし、今後ホテルステイで参加する人には「その町をとことん知り尽くして、友達を案内できるくらいになること」を一つの目標にしてほしいと思います。
ホテルでの共同生活で努力したこと
ホテルステイで努力したことは、ホテルのスタッフの方と積極的に英語でコミュニケーションを取ることです。英語力をつけることがこのプログラムの目的の一つだったので、英語を使う機会を自ら作り出すことを意識していました。
具体的には、英語のプレゼン資料をスタッフに見てもらい、使っている英語が正しいか添削してもらったり、セキュリティの方と日常会話をしたりしました。その結果、ホテルで会うたびに挨拶する仲になったり、仕事や文化について話せたりと、日々の生活の中に英語のやり取りが自然に組み込まれていきました。
ホームステイに比べて、ホテルステイは英語を使わずに生活できてしまう面があると思いますが、自分から話しかけることで十分に「英語を使う」ことは可能です。3週間の中で、ホテル内でも外でもたくさんの人と関わりながら、充実した時間を過ごすことができました。
本プログラムを体験してみて
本プログラムで得られたことと、今後の活かし方
このプログラムに参加して得られた一番のことは、「自分から行動しなければ何も変わらない」ということです。これはビジネス研修でも実地研修でも強く感じました。
ビジネス研修中、アメリカでは「質問しない=興味がない」と思われるという文化を学びました。日本では遠慮や空気を読むことが美徳とされがちですが、アメリカでは積極的に発言することが信頼や関心の表れとされます。その違いを実感し、研修ではできる限り質問や発言を心がけました。
また、UCLAの学生とのディスカッションでは、自分の意見を堂々と発言する彼らの姿に刺激を受け、「この人たちが将来のライバルになるのだ」と強い危機感も覚えました。彼らに共通していたのは“発信力”や“行動力”でした。私ももっと主体的に動かなければならないと感じ、実際の行動に移すことの重要さを改めて実感しました。
実地研修では、それを「実践」の中で体験することになりました。誰かが何とかしてくれるだろうという“他責”では、チームは前に進みません。わからないことがあれば自分で質問する、聞いてほしいことや決めたいことがあるなら自分から動く。そうしないと、複数のタスクが同時進行する現場では時間が足らず、成果を出すことはできませんでした。
この学びは、今後の大学でのグループ活動や課外活動、そして就職してからの社会人生活においても間違いなく活かせるものだと思います。特に「自分の行動で現状は変えられる」という実感は、今後の自信にもつながりました。
このプログラムを後輩や友人に薦められそうですか?
Yesであれば、その方々へメッセージをお願いします!
Yes!
ぜひ私は参加してほしいと思います。なぜなら、自分の常識や価値観を壊せる体験ができるからです。
私自身も、当初掲げていた2つの目標(必要なスキルの習得と英語力の向上)を達成できたと同時に、アメリカでの生活を通して現地のマインドや国民性を学びました。そして、それによってこれまで自分が持っていた価値観や考え方が大きく変わりました。
特に印象的だったのは、アメリカという“人種のサラダボウル”の中で生活する人たちは、「思考の自由が尊重されており、自分の意見を言うことに対して自由である」という点です。その価値観を知り、自分にもしっくりくるものだと感じました。私はアメリカの食や街の衛生環境など好きになれなかった部分もありますが、この“自由を信じるマインド”についてはとても共感でき、好きになれました。
こういった気づきや学びというのは、実際にアメリカに行って生活してみないと得られなかったことだと思います。ネットやYouTubeでは本当の意味で理解することはできなかったと思います。
英語や問題解決スキルは日本でもある程度学べるかもしれません。しかし、アメリカLAという“異文化の環境”に身を置きながらそれらを学ぶからこそ、本当の意味での成長や自己理解につながるのだと思います。
殻を破って自己理解を深めたい人、自分のスキルを一段上に引き上げたい人には、このプログラムはとてもおすすめです。絶対に参加して後悔しない経験になると、私は断言できます!