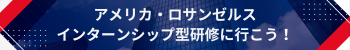インターンシップ体験談:IT系企業
筑波大学理工学群 1年生(参加当時) 吉田晏大さん

参加理由
- 日本のブラック企業問題に関心があり、労働生産性の高いアメリカでインターンを行うことで、日米の働き方の違いを知りたかったから
- 将来的にカリフォルニア州で1年間交換留学したかったので、まずは実際に現地へ行ってみようと思ったから
参加する前に思っていたこと
- 合同ビジネスプログラムやインターンを通じて、すべてを吸収してやろうという気持ちでした。
- ホームステイが初めてだったので、英語でしっかりとコミュニケーションできるか、自分の考えを伝えられるか不安でした。
インターンシップについて
実習先の日々の仕事
ミーティング出席、ミーティング準備、レポート提出、読書、データ入力、Cloud ERPに関する市場調査、倉庫整理、給与計算、ホワイトボードのペインティング、HRの方へのインタビュー、プレゼンテーション
実習先での1日の流れ
- 8:45 インターン先に到着。
- 9:00 データ入力。ダイレクトメールを送るため、取引先企業を紙からエクセルへリストアップ。
- 10:30 ミーティングに出席。会計や営業、誕生日会の企画まで英語で行われる様々なミーティングに参加しました。
- 11:30 読書。稲盛和夫さんの考え方や、働き方についてインプット。
- 12:30 Developingチームの方々と昼食を食べに行く。
- 13:30 ERPに関するリサーチ。資料作成。
- 16:00 Snackタイムと4時ウォーク。会社の取り組みとして、4時ごろにおやつを食べ一休みしたり、会社の周りを3周歩いてリフレッシュしたりする文化がありました。
- 16:15 倉庫整理やホワイトボードへのペインティングなど。
- 17:30 業務終了
※上記は一例で、ルーティンワークではなく、毎日様々なことをしていました。
実習で印象深かったこと、大変だったこと

実習中に最も努力したこと

本プログラムを体験してみて
本プログラムで得られたことと、今後の活かし方
- 視野が広がり、少し高い視座を得ることができました。日米における働き方に関する知識だけでなく、様々な考え方や生き方に出会いました。その中で、現在交換留学だけではなく、海外大学への編入も検討しています。
- 日本全国から参加し、現地でできた友人や、実習先、ホームステイ先で非常によくしてくださった方々とのご縁。帰国後も会いに行きました。
- 自分のリスニング力の無さを痛感しました。これは帰国後のIELTS受験に向けて良いモチベーションになっています。
このプログラムを後輩や友人に薦められそうですか?
Yesであれば、その方々へメッセージをお願いします!
 Yes
Yes
「将来は留学を」「いつかは海外で学んだり働いたりしてみたい」そう思っている方がいらっしゃるなら、出来るだけ早く行ってみるべきです。なぜなら、現地に行ってから初めて見えてくることもたくさんあるからです。私は今回、旅行ではなくインターンという形をとったため、アメリカで働いたり学んだりしている方々とお話する機会が多く、日米の働き方の違いについて知るには非常に恵まれた環境でした。自分の目的や目標を持ち、それに合わせてプログラムや実習先企業を選んでもらえればと思います。まずは一歩踏み出してみましょう!
※こちらの記事は、2024年9月までの本プログラムを運営していたLighthouse (Career Encourage USA)社が主催していた時期の体験談です。